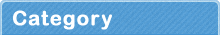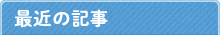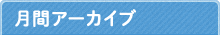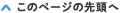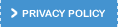2024年度助成金交付先団体 活動報告書

NPO法人里親子支援機関えがお
https://osaka-satooya.com
【テーマ】第5回えがお絵画コンクール
【応募作品数】 132作品
【表彰式】 3月20日
【入賞作品展】 ベアーズ1階ギャラリースペース、
門真市民プラザ1階、
モノレール「小路駅」ものギャラリー
【観覧者】 延べ3000人
2025年も第6回えがお絵画コンクールを開催予定です。第5回は近畿里親会の方が参加が少なかったので、もっと早くから声をかけていき、足を運んでいきたいと思っています。また、第5回までは冬休みに絵画を募集していたのですが、長いお休み中に描いていただくことができるよう、第6回は夏休みに募集を変更。132作品から200作品になれるよう、支援機関や施設を回って声がけしていきたい。そして、第10回までには近畿里親会から、西日本、全国へと広げていけるように、啓発活動を広げたいと思っています。
まず、過去最高の応募数実績は大きな喜びです。家族と離れて生きている子どもと、それを支える里親や児童養護施設スタッフたちは、今年一番の「えがお」をテーマにお絵描きの温かい時間を共有し、互いの心を開放し感情にふれあい、応募をしてくれたのです。どの作品も力強く、楽しく、訴えかけるものがしっかりとありました。授賞式での子どもたち、里親、施設スタッフ、
ケアリーバーは、自信と絆を感じ、家族の意味もかみしめたことでしょう。国際的に後れを取っている日本の社会的養護・里親制度が見直されつつあります。支援者も子どもも、手放さなければならなかった実親も参加できる時間が提供できたことがまだ日本では奇跡のようなことなのです。私たちが求めていかなければならない姿、理想です。あの姿をそっと見つめられたこと、関係機関の大きな協力を頂けたことも、本当にありがたいことです。ありがとうございました。
ひといろプロジェクト
https://www.hito-iro.com
【テーマ】入院・通院中の患者・家族・医療従事者に、ケアにつながるアートとの関わりを~アーティストと協働し、地域のアートセンターと連携するホスピタルアート活動
1)高槻病院・小児病棟:プレイルームにて、ワークショップ開催 患者や家族医療従事者が参加 アーティスト池平撤兵氏とつくる絵画コラージュ作品を制作した。(約50名が参加)
2)大阪府立江之子島文化芸術創造センターでのホスピタルアート展(約300名が来場)内容は新聞3紙(朝日、読売、産経)に取材掲載された。
3)大阪母子センター・入院中の小児患者が集まる院内の創作の会(10名が参加)たかはしななさんと、病院を明るくするために自分で描くマルチクロス制作
4)大阪母子センター・入院中の小児患者が集まる院内の創作の会(10名が参加)井上信太氏(作家はオンラインで参加)と楽しむマグネットボード制作
完成品としてのアートの良さを第一目標にするではなく、私たちのように、入院中・通院中の患者や家族、医療従事者の方々のケアにつながるアート活動を外部団体から病棟に持ち込む事例はまだ少ない。スタッフの人員のこと、資金確保のこと、病院の受け入れの問題など、課題はたくさんある。だからこそ院外のアート展により、この活動を社会と共有し認知や理解を深めることが今後の可能性につながるし、院内の患者様の展示への遠隔体験ができる機会と考えている。時間はかかりそうではあるが一般社団法人化にむけて、私たちにしかできない事業を安定して活動してゆきたいと考えている。想いのあるアーティストや仲間づくりも大切にすることが、今後の可能性につながるので一つ一つ丁寧に、ホスピタルアートの活動に東奔西走している。
つるはしにほんごきょうしつ
https://tsuruhashinihongo.wixsite.com/japaneseh
【テーマ】地域に暮らす外国人を対象とした日本語サポート事業のさらなる充実
毎月第2、第4日曜日の午前11時から12時半の時間に、大阪市天王寺区にある民間レンタルスペース「min-pack」にて日本語学習サポート活動(日本語教室)を開きました。当活動は、当団体の中心活動で、地域に暮らす外国人一人ひとりの日本語能力にあわせ、日本語ネイティブボランティアがマンツーマンや小グループ単位で学習サポートするものです。2024年度は前年度定着していた学習者が、以前通っていた日本語学校の友人・知人をたくさん連れてきてくれ、彼ら・彼女らが安定的に参加したこと、また、同じ天王寺区にある大阪国際交流センターから、多くの学習者を紹介していただき、学習者の延べ参加者数および平均参加者数が、昨年度に比べ増加しました。
日本語の面白い表現や日本独特の文化の紹介、日本語を使いつつ参加者間交流を促進するアイスブレーキング、小グループのクラス活動、アンケート、今後のスケジュール確認後、教室が終わると、近くの飲食店に行ってランチをします。今年度は、イベントとして、ハイキングやクリスマス会を開催し、ボランティアや学習者の親睦と交流を図りました。また、ボランティア研修を行い、日本語教師を招き、学習者と初対面で交流する際のポイントなどを教えてもらいました。そして、発話しやすい環境づくりと主体的なアクションを引き出すことについて、日本語学校での実践例を交えながら学びました。結果として、多様性を尊重するという中心価値観を深めるため、一人一人が大切にされ、公平に扱われていると思えるためのコミュニケーションやファシリテーションについて学ぶ機会になりました。
2/1には映画「ワタシタチハニンゲンダ」上映会を行い、在日朝鮮人の管理政策から始まった日本の外国人政策の歴史と課題について網羅的に学べました。特に技能実習生制度や入管収容の問題について、当技能実習制度とその廃止に伴い大体運用される育成就労制度について、法律的な説明を代表の劉から行いました。
当会は活動目的として、日本に暮らす外国人の日本語能力向上とともに、暮らし全般をサポートすることにしています。学習者が教室の参加者という立場にとどまらず、コミュニティーでの居場所を確保するためには、ありのままの自分でいられることが基本的条件となるので、ニーズが充足されていること、役に立っていることが実感されていることが必要になる。
そうした観点で、次年度の事業を計画しています。
①学習者へのインタビューを行い、その中でニーズを確認していく。
②N2合格を目指したJLPT対策講座をボランティアメンバーが専担講師になり、希望者に実施する。
③学習者の能力を発揮する事業
(1)中国語講座開設の応援、母語を活かした市民講座を開設できないか模索する。講師希望者には、広報、場所についての金銭支援を行う。
(2)大阪万博・旅レポ発表会を開催する。
④学習者の本音やニーズを引き出すファシリテーション力向上に資する研修を、外部講師を招請して開催する。
特定非営利活動法人つながりひろば
https://tsunagari.osaka.jp
【テーマ】がん患者、心と身体をいやす農作業「つながりファーム」で、がん患者支援
『つながりファーム活動』がん患者の多くが抱える不安や悩みを相談できる場所を探しています。また、がんの診断から治療の過程で体を動かす機会が減少することは筋肉・体力が減少し運動機能の低下や倦怠感を生じることにつながっており、適度に体を動かすことは治療の副作用軽減、QOLの向上にも非常に重要です。
農作業を通じ土と触れ合うことで自律神経を整え、気持ちを安定させるセロトニン効果も期待できることから、がん患者と共に活動を始めたのが「つながりファーム」活動です。
「つながりファーム」は大阪府柏原市の、ユニバーサル農園「ディーセントファームかしわら」の一画を農園体験用につながりひろばで借りたもので、毎週金曜日午前中にファームに集合し90㎡の農地に季節毎の種や苗を植え収穫しました。
夏季は朝9時頃、冬季は10時頃に集合し2〜3時間の作業。年間52週のうちゴールデンウィーク、お盆、年末年始の4週以外の48週、活動を行いました。
参加者が、がん患者対象となるため、体調を優先し無理をして参加することが無いようアナウンスもしていることから参加者数は一定しませんでしたが、多い時で15名、少ない時でも7名が参加し、農作業を行いました。
また、つながりひろばが活動できない金曜日以外の日には、障害を持った方や引きこもりの方にもお手伝いをお願いしています。障害を持った方たちが農業分野で活躍することを通じ、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく医農福連携、そして「SDGs 3.すべての人に健康を」としても取り組むことができました。
『栄養食事サポート』つながりファームで収穫した野菜を使った食事栄養サポートイベントとして、つながりひろば(大阪国際がんセンター患者交流棟2階)で3回の食事会を実施しました。がん病態栄養専門管理栄養士に食事のメニューの監修・講師を依頼し、野菜に含まれる栄養や身体が喜ぶ食べ方等の講義を聴きながらの食事、患者同士の交流ができるイベントになりました。
・2024年5月11日(土)11:30〜14:00「つながりファーム新鮮野菜の食事会」
参加者総数:23名(講師、スタッフ含む)
・2024年10月31日(木)12:30〜15:00「つながりファーム秋野菜でハロウィンパーティ」
参加者総数:21名(講師・スタッフ含む)
・2025年1月18日(土)11:30〜14:00「つながりファーム新鮮野菜の食事会」
参加者総数:19名(講師・スタッフ含む)
参加者からファーム活動に参加することで、身体も心も元気になったとの感想をいただいており、参加者の表情からも拝察することはできますが、それらは客観的に判断できるデータはないので、今後、測定機器を購入し参加者の身体的・精神的ストレス度、血管弾性度の変化、自律神経均衡度や気分の変化についてのデータを定期的に収集し、農作業がもたらす患者への影響等の調査も計画しています。参加者にとって夏の暑さや冬の寒さ、雨天などの環境では体への負担も大きくなることもあります。また、せっかく育てた農作物も獣害被害を受けました。
これらの課題に対して今後も作業環境を整え、より多くの患者に参加頂けるようファーム活動に取り組んでいきます。
財団よりメッセージ
申請書を拝見して審査会で交付先を決定した時、それぞれの団体の活動を想像し、
わくわくしていました。4団体それぞれ事業内容は異なりますが、参加者や利用者に寄り添うことを大切にされているところは、共通していることがわかります。
それぞれの団体が今後の課題を明確にされ、活動の継続、そして活動の拡大に向けて進んでいらっしゃることに感服いたしました。
ますますのご活躍を、楽しみにしています。